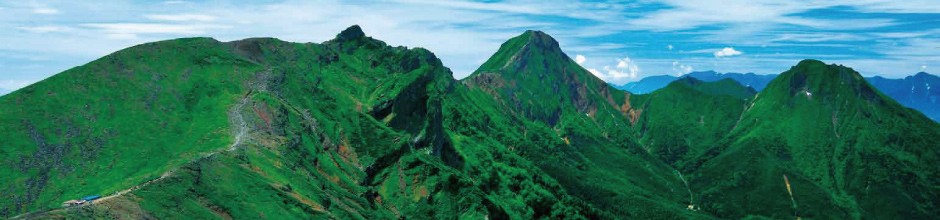第22回八ヶ岳フォトコンテスト
全国から103名、302点のご応募をいただき誠にありがとうございました。(敬称略)
【総評】
本コンテストも今回が22回目。身内(山小屋関係者等)の作品が多くを占めていたスタート時をおもうと隔世の感がある。ずいぶん一般に滲透したものだと審査に携わるひとりとしてうれしくおもう。今回の審査の席上、論議の的になった点をひとつ今後の参考のために記しておく。平地における撮影の作品の場合、どこまでを「応募規定内」として容認するかということ。今回の応募規定には「八ヶ岳に関する自然風景」とある。この「関する」をどう解釈するかになるわけだが「八ヶ岳が・・・写っている自然風景」―あらまし、そう受けとっていただいていいだろう。他の面においても応募規定はぜひお守りいただきたい。せっかくの労作がつまらぬことで審査の対象外になってしまってはだいなしである。(新妻喜永)
金賞(茅野市長賞)
染まる岩稜
脇坂 恭司(東京都町田市) 撮影地:阿弥陀岳南稜
【選評】
朝陽に色づく阿弥陀岳南稜である。屹立する岩峰群が適度な明暗対比をもって動感ゆたかに描かれている。主眼の岩峰を中央に据えて画面の安定を図った構成が動感との調和において効果的。「八ヶ岳にこんなところあったかな」と人目を驚かす「新鮮な被写体」も魅力だ。仄聞するところによれば作者は近年、阿弥陀岳南稜の撮影に専心しているとのこと。その「こだわり」が生んだ秀作といってよかろう。
銀賞(茅野商工会議所会頭賞)
残照
矢崎 政安(長野県諏訪市) 撮影地:乙女滝
【選評】
「絵になる場所」というのは、じつは絵づくりのむずかしい場所である。被写体側の「絵になる力」が強いほど自分なりの作品をものにするのはむずかしくなる。「絵になる力」に伍して闘えるだけの力量が必要になる。本作品は横谷峡乙女滝を被写体としたもの。「絵になる力」を利用しながら作画上での選択(撮影地点、光線、画面構成等)に独自性を発揮しオリジナリティのある乙女滝をつくりだしている。幻想的な作品だ。
銀賞(茅野観光連盟会長賞)
秋の湖
輿石 浩(長野県岡谷市) 撮影地:白駒池
【選評】
色彩ゆたかな写真に接したとき、選者はかならず「もしこの写真から色をとりのぞいたなら」とモノクローム的な見方をしてみる。「色」のほかになにがあるかがはっきりするからである。この作品のおもしろさは、いうまでもなく鮮烈な色彩感にある。しかし、ただそれだけではない。明暗のコントラストもそなわり画面構成の妙(水辺の紅葉にたいする水草の配し方がうまい)も感じられる。内容度の高い作品である。
銅賞(小海町観光協会長賞)
降雪の午後
福井 一夫(埼玉県狭山市) 撮影地:中山峠
【選評】
題名から推測するところ風雪がおさまった直後の撮影のようである。荒天明けは新雪の化粧によって雪山がもっと雪山らしく美しくみえるとき。折しも山は山容表現にうってつけの斜光線状態。そうした好条件に遭遇して爽快感に富む作品をものにしている。撮影地は中山峠近くの通称展望台。ここはだれもが写す天狗岳撮影の人気ポイントでしたがって被写体に新鮮みはないが絵づくりそのものは確かだ。
銅賞(佐久穂町観光協会長賞)
光射す雪壁
山下 研作(神奈川県平塚市) 撮影地:赤岳鉱泉
【選評】
厳冬の横岳西壁は、八ヶ岳を代表する景観のひとつ。高い人気の被写体でもあり、過去、数多くの作品が発表され本コンテストにも毎回かならず何点かの応募がある。選ぶ側、見る側にしたら「またか」というのが偽らざる気持ちだ。その「またか」の気持ちを粉砕しないことには勝利はむずかしいわけだが、本作品には「またか― しかし、わるくない」とおもわせるだけの強い力がある。完璧な画面づくり。迫力満点の傑作だ。
銅賞(八ヶ岳観光協会長賞)
荒天寸前
新井 純子(埼玉県北本市) 撮影地:地蔵の頭
【選評】
地蔵ノ頭からみた横岳である。霧に没する寸前の模糊たる山稜上部が荒天へとむかう山にある登山者の不安感、重苦しさを象徴していて効果的だ。その登山者ふたりは同行者かそれとも……。いずれにせよ、いい位置にいてくれたものである。山稜の状態と登山者の位置とふたつの好条件がかさなった一瞬を手ぎわよく写しとっている。「写真的な山」におぶさらなくても作品はつくれるものである。その好見本といっていい。
ラムダ賞
晩秋の頂
鈴木 秀樹(神奈川県川崎市) 撮影地:権現岳山頂
【選評】
草もみじと緑のハイマツと霧氷の岩峰と、これらが一体をなす近景を主題にさらに中景として三ッ頭、遠景として富士山、白雲を配して作画している。被写体の数は六つ。しかもそのひとつひとつに力の差があまりない。画面に繁雑さを感ずるのはそのせいであろう。季節感、遠近感に富む上作ではあるが被写体配合が少々気になる。霧氷の岩峰をもっと際立たせた撮り方をしてもよかったのではないか。
モンベル賞
頂への道
荒田 道(神奈川県横浜市) 撮影地:赤岳頂上
【選評】
赤岳山頂からみた朝焼けの横岳稜線である。使用カメラの記載がないので定かではないが、おそらく300ミリ程度(35ミリ判カメラで)の超望遠レンズによる撮影であろう。望遠レンズ特有の積み重ね(圧縮)効果によって岩峰群が鋸歯状に表現され迫力を強めている。明部と暗部との色の対比もあざやかでその配合もいい。気になるのは題名。選者なら素直に「朝焼けの岩稜」とするか、ちょっと気取って「岩稜燃ゆ」とでもするが。
信濃毎日新聞社賞
黎明権現岳
輿水 忠比古(山梨県北杜市) 撮影地:権現岳
【選評】
日の出にちかい朝方の撮影である。やや白みがかかった空の部分に「黎明」が感じられる。シルエットの山ふたつ、権現岳と富士山とを遠近に対峙させその間隙に甲府盆地を配して光の洪水を際立たせている。盆地上空にたなびく雲の帯が幻想的で山小屋のものとおもわれる富士山の明かりも興味深い。内容のある夜景写真だが、明け方ちかくの撮影で空があかるく星の軌跡が不明瞭になってしまったのがはなはだ残念だ。
長野日報社賞
山麓の春
山田 英雄(静岡県静岡市) 撮影地:須玉
【選評】
山はまだ冬。しかし、里はすでに陽春。雪の連山と菜の花畑との対照を軸に山国の春を季節感たっぷりに作画している。四月下旬の撮影である。技術面をいうなら稜線の切りとり方も近・中・遠景の配分も画面の左に寄せた人物配置もふたりの人物の捉え方もすべてが的確だ。スナップショット的な撮り方でこれだけまとまりのある画面をつくれる腕前はみごとというほかない。赤いTシャツが好アクセントになってもいる。
茅野市民新聞社賞
山麓冬景
山岸 順三(長野県岡谷市) 撮影地:原村
【選評】
原村のまろやち湖が撮影地という。結氷をはじめた池と冬枯れのシラカバ林と新雪の山とで構成された画面は、つめたさのなかにもぬくもりのある初冬の空気をよくつたえている。ひとつ残念なのは、近景をなす水面の扱いにものたりなさがある点だ。三つの被写体のなかで表情のもっともおもしろいのはこの水面であろう。これをもうすこし多く撮り入れてほしかった。いちだんといい絵になったにちがいない。
努力賞
八ヶ岳山麓の夜明け
小林 茂良(長野県茅野市) 撮影地:茅野市
【選評】
雲間に朝陽がのぞく空と白花を満開にしてひろがるソバ畑との組み合わせ。露出設定のむずかしい場面にもかかわらず、両者をバランスよく表現し美しい絵柄に仕上げている。これ以上どちらに露出がかたむいてもこれほどすぐれた画面にはならなかったであろう。写真的にはもっと上位に入賞してもおかしくない出来であるが、惜しむらくは「八ヶ岳」がほとんど描かれていない。それがマイナス点となった。
夕照
千村 信(山梨県甲斐市) 撮影地:南蓼科
【選評】
独立峰や独立峰のようにみえる山を被写体にする場合、第一に問題になるのが「山頂の位置」である。画面中央に置くかそれとも左右にずらすか。山の両側斜面の起伏状態や雲の有無等条件により異なってくるわけだが作者はここでは大きく左に寄せている。右端にわずかにのぞく青空を入れたいがための処置であろうか。若干左に寄りすぎた感がなくもないがといってさほどバランスがわるいわけではない。
静かな湖
桜井 勝美(群馬県高崎市) 撮影地:御射鹿池
【選評】
カラマツ林の淡い緑とシラカバの黄みがかった緑と水辺の草の濃い緑と、これら三者による「緑のハーモニー」がこの作品のテーマであろう。直線的なカラマツ林と二本のシラカバのなよやかな姿かたちとの対照にも妙がある。男性コーラスをしたがえて歌う乙女姉妹、といった感じがしなくもない。水面をもうすこし多く配してもよかったようにおもうが、ともかく新緑をしっとりと表現した趣のある作品だ。
竜神の栖(すみか)
遠又 康子(岐阜県各務原市) 撮影地:白駒池
【選評】
この作品をみたとき人はどんな反応をしめすであろう。「なんだこれは」とある人は顔をしかめるかもしれない。またある人は「へえ、おもしろいじゃない」と共感するかもしれない。好悪の対立が予想される奇抜な作品である。絵柄が奇抜なら針葉樹の形状を竜に見立てた題名も奇抜だ。こうした独り善がりととられなくもないものの見方は貴重だ。作者にはさらに磨きをかけてもらいたい。
夜明けの山稜
福田 雄一郎(東京都多摩市) 撮影地:権現岳
【選評】
権現岳山頂一帯は四方に壮観をもつ一級の展望台。写真愛好家が集う撮影ポイントでもある。なかでも愛好家に人気の高いのが赤岳、阿弥陀岳を望む北方の景観。この作品もそれを被写体にしている。朝焼けの山肌と霧氷の斜面との対照を中心につくられた画面は類形的である以外に難点はない。この場面、スカイラインをカットした絵柄もおもしろいようにおもわれるが作者はそうしたものを写してみたであろうか。
蒼い大地
八掛 良一(埼玉県川越市) 撮影地:佐久穂町
【選評】
佐久穂町としか撮影場所の記載がないが、北八ヶ岳のどこかであろう。苔むす岩群が精緻な描写で捉えられている。こうした被写体では岩塊をどうバランスよく配するかが一番のポイントになるが、その点はまとまりがあり級第だ。右下の新緑がいいアクセントになっている。選者なら左端の樹木と下端の小さな岩をカットし(アクセントの新緑を若干切ることになるが)上方の樹林をもうすこし入れるが ― どうだろう。
夕光に輝く坪庭
内野 保(埼玉県川越市) 撮影地:坪庭
【選評】
おだやかな夕景色である。むやみに露出をきりつめたりせず日陰の部分を明るく描いているのがいい。画面構成はもうひとつだが好感のもてる作品だ。「もうひとつ」のひとつとは、近景をなす坪庭の岩塊の配置がやや散漫な点。画面のほぼ中央にある一群の岩をもっと大きく捉えてこれを画面の目玉にするとよかった。ポジションの移動は困難でもズームレンズ(データ欄に記載がある)ならできたかもしれない。
水面に映える茜雲
安藤 紀嗣(長野県岡谷市) 撮影地:八千穂レイク
【選評】
正直いって選者は最初のうちこの作品をさかさまにみていた。少々妙だなとおもいながら人に指摘されるまで気づかなかった。 ― 倒影だけが被写体の作品というのはあんがいめずらしい。思いきったフレーミングに作者の主張が感じられる。倒影にわずかな乱れもないところをみると、水面はまさに鏡のような状態だったのだろう。だからこそつくりえた作品といっていい。選者が騙されたのもそのためだ。
風疾る
山下 和人(長野県茅野市) 撮影地:坪庭
【選評】
「左下の雪面が目障りだなあ」というのが作品をみての第一の感想。中途半端にはいりこんだこの邪魔物を画面外へ追いやるだけではるかに調和のとれたいい作品になる。さらにつけ加えるなら手前の風紋の雪面にもう一、二歩近寄りこれをもっと大写しにしてみたかった。以上は坪庭という思うようには動きまわれない場所柄を知ったうえでの「無理な注文」である。作者もきっとはがゆい思いをしたことだろう。